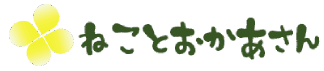今回も養成講座を受講しての感想です。先週の投稿で、「後見人を立ててください。」と銀行に言われて、後見人制度を利用し始めるケースが多い、と書きました。
後見人養成講座を受けて思うのは「そんなに簡単に言わないでよ」です。
親族後見人になるための手続きを簡単にまとめると、
①成年後見の申立てに必要な書類の準備。
– 申立書(家庭裁判所で入手可能)
– 申立をする人の戸籍謄本
– 本人(被後見人、わたしの場合は母)の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書
– 本人の診断書(主治医による精神状況などに関するもの)
– 本人の財産に関する資料(通帳のコピー、不動産登記簿謄本など)
– 後見人候補者(親族=わたし)の住民票、身分証明書
②家庭裁判所への申立て
③家庭裁判所による審理
– 申立書類の審査
– 本人(母)との面接
– 後見人候補者(希望はわたし、でも誰かかも)との面接
– 必要に応じて本人(母)の精神鑑定
– 親族(わたし)への意見照会
④後見開始の審判・後見人選任
(必ずしも申立てで希望した候補者(わたし)が選ばれるとは限らない。)
⑤審判確定後の手続き(わたしが選ばれると、わたしがやらなきゃいけない事)
– 法務局での後見登記
– 各種金融機関等への後見開始の届出
– 財産目録の作成・提出
①から⑤まで2〜4ヶ月程度かかるそうです。申立ての件数が多くて、審理が始まるまでの順番待ちの日数が影響するんだそうです。
しかも申立手数料、主治医の診断書、登記手数料(場合によっては鑑定費用)など、合計で数万円程度が必要! もし親族(わたし)以外の人が後見人となれば、その後はずっと毎月費用が発生します。ちなみに利用金額は、裁判所が「本人(母)」の資産・収入金額を見て決めます。
AIによると「複雑な手続きのため、司法書士や弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。」だってさ。だったら専門家への相談料もいるよね?
【相続・家族信託ガイド|司法書士・行政書士事務所リーガルエステート】 のサイトより「成年後見制度のデメリットとは」を読むとさらに利用したくなくなります。
ね? ここで4行目に戻る。「そんなに簡単に言わないでよ」
やっぱりアレでしょ? 主教団体への巨額の寄付金。判断能力が低下した人の預金の払い戻しなどをしたら、後から本人の相続人から取引の無効を主張されたり、銀行が責任を問われたりするリスクがあるから。 リスクを負いたくないだけだよね?