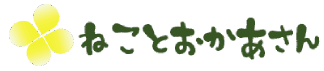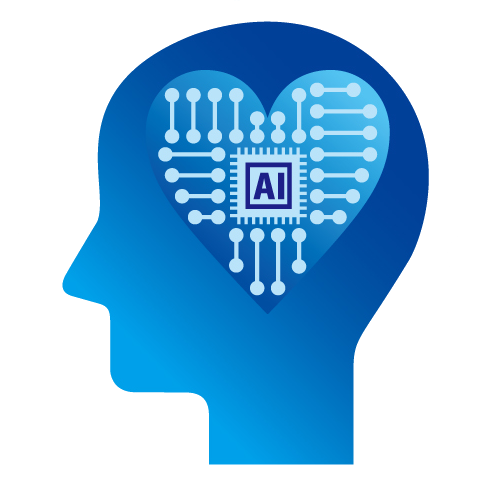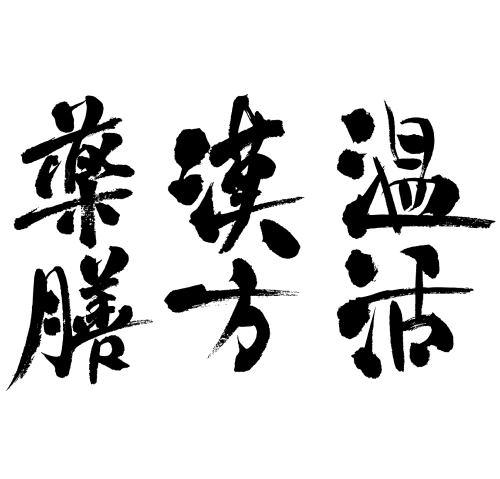今回は認知症発症リスクの36個の内の4つ目、血行不良の話です。血行障害、血行不良、血流障害は、だいたい同じ意味です。「血行」とは、血液が体内を巡ること。「血流」は字のごとし、血液が流れること。
血の巡り・流れが悪くなると、酸素や栄養が体に行き渡りにくくなります。脳の酸素不足は、神経細胞の機能障害を起こし、脳の栄養の偏りは神経細胞の破壊を起こして、認知症発症のリスクを高めると言われています。
原因は4つ。
①寒いと血管がキュッとなって流れる量が少なくなる。
②血がドロドロになって、スムーズに流れない。(脂質の過剰摂取)
③血管に悪玉コレステロールが付着して流れるスペースが小さくなる。
④血管が傷つき、血管の内側が厚く固くなって流れるスペースが小さくなる。(加齢や喫煙・飲酒、糖分の過剰摂取など)
②③④は生活習慣を見直さないといけません。規則正しい睡眠習慣や食生活、適度な運動、ストレスケアなどなどなど。②③④が原因の血行不良は、血管年齢検査を受けることでわかります。
問題は①、身体が冷えること。そう、「冷え症」。
わたしも母も妹も「冷え症」です。年中手足は冷たく、冬には「触らないで」って言われるくらい冷たいです。という事はみんな「血行不良」と言えます。
「冷え性」は西洋医学では病気として扱われません。「そういう体質だ」という位置付けです。なので薬物治療はありません。
薬がないなら、物理的な対策に頼るしかありません。温かい物を食べるとか飲む。体を温める食材を食べる。いわゆる温活ですね。

上の食材意外だと、一般的に冬が旬の野菜は体を温めますね。逆に夏が旬の野菜は体を冷やします。
そして暖かい環境。冷房で体を冷やし過ぎない。わたしは職場では1年中、夏でも温度が高くて体を温めるお茶を飲んでいます。色の薄いお茶は身体を冷やし、色の濃いお茶は身体を温めるそうです。もちろん冬は完全防寒対策をしないと手が動きません。
だけど、「血行不良」と「体の冷え」って「ニワトリ」と「卵」みたいですね。どっちが先?って。
②③④を改善して血行をよくすると体は温まる。それでも体温が上がらないなら、①の体質だから、体を温めて血行をよくする。で、血行がよくなると体は温まるんですよね…?
どっちが先だと思いますか?
今日は西洋医学で言われている事を中心に書きました。東洋医学の漢方薬については、また次回。長くなりそうなので。